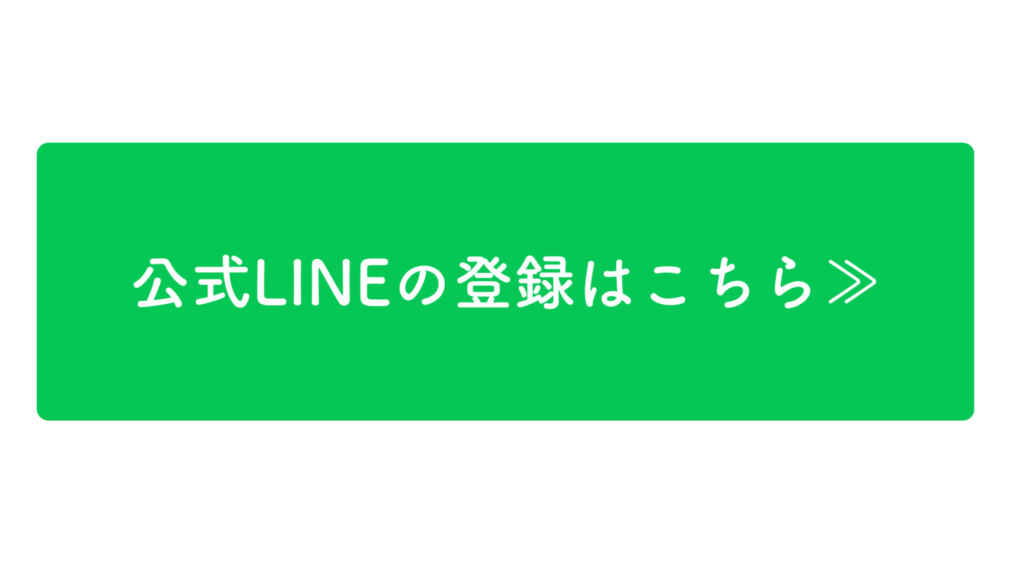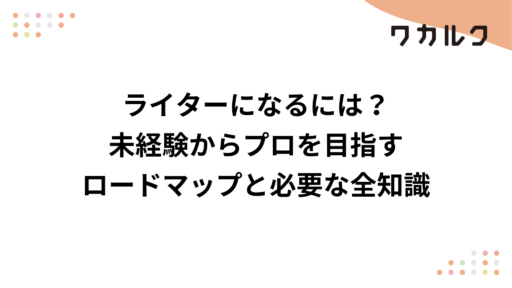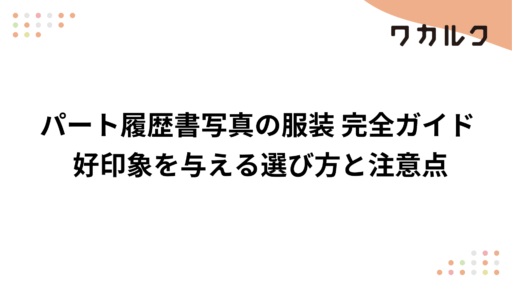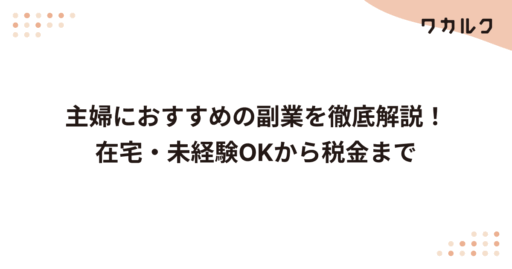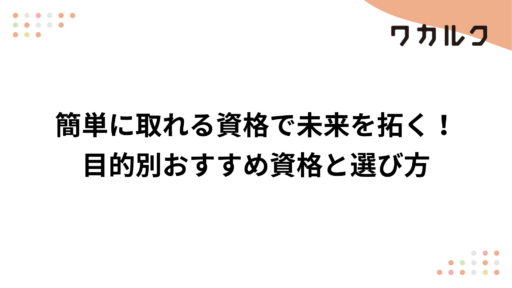
扶養内勤務とは?年収の壁と税金・社会保険の仕組みを徹底解説
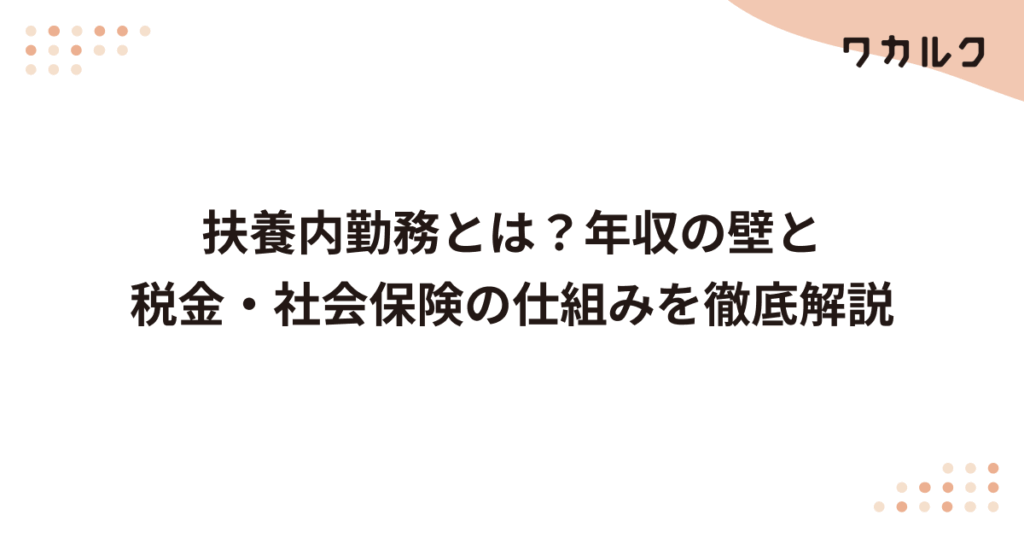
パートやアルバイトで働く際に意識する「扶養内勤務」。しかし、「103万円の壁」「130万円の壁」といった言葉だけが先行し、その複雑な仕組みを理解しないままでは、かえって手取りが減ってしまう落とし穴が待っています。実は、扶養には「税金」と「社会保険」という全く異なる2つのルールが存在し、近年の法改正でその内容は大きく変化しています。この記事では、専門的な扶養の仕組みを誰にでも分かりやすく紐解き、最新の制度変更に対応した具体的な働き方のポイントを解説します。最後まで読めば、あなたは自身のライフプランに最適な収入ラインを見極め、手取りを最大化しながら安心して働けるようになるでしょう。
目次
1.扶養内勤務の基本を知ろう

1.1扶養内勤務とは?その定義と概要
扶養内勤務とは、配偶者や親などの扶養に入ったまま働くスタイルを指します。重要なのは「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」という2つの基準を同時に意識し、年収や労働時間を調整する点です。税法上は配偶者控除などが適用される範囲、社会保険上は健康保険や年金保険料の自己負担が発生しない範囲で働くことを目指します。
1.2.扶養には2種類ある 税法上の扶養と社会保険上の扶養
税法上の扶養は、所得税や住民税の計算に影響する制度です。扶養に入ることで、世帯主の所得から配偶者控除などが差し引かれ、世帯全体の税負担が軽減されます。2025年の税制改正では、基礎控除と給与所得控除が引き上げられることに伴い、所得税が課税されない年収の上限(いわゆる「103万円の壁」)が実質的に123万円に引き上げられる見込みです。これに合わせて配偶者控除の対象となる年収上限も変わるため、税法上の扶養範囲は実質的に拡大します。
一方、社会保険上の扶養は、健康保険と厚生年金保険の加入義務に関わる制度です。厚生労働省によると、従業員数51人以上の企業に勤めるパートタイマーは、週20時間以上働き、年収が106万円以上になると社会保険の加入義務が発生し、扶養から外れます。さらに同省は、この年収106万円という要件を2026年10月を目処に撤廃する方針を発表しており、将来的には労働時間が主な基準となる見込みです。
このように、税法と社会保険の扶養は目的も判定基準も全く異なります。例えば、年収を123万円以内に収めても、勤務先の企業規模や労働時間によっては社会保険料の負担が発生する可能性があります。この二重構造を正しく理解することが、扶養内で賢く働くための第一歩です。
1.3.扶養内で働くメリットとデメリット
メリット
- 所得税と住民税が非課税、または大幅に軽減される
- 配偶者の社会保険に加入できるため、健康保険料や年金保険料を自己負担しなくて済む
- 家事や育児など、ライフスタイルに合わせて柔軟な働き方が可能になる
デメリット
- 年収上限をわずかに超えただけで社会保険料の負担が発生し、手取りが大きく減少する「働き損」のリスクがある
- 厚生年金に加入しないため、将来受け取る年金額が少なくなる可能性がある
- 収入を抑えることで、キャリアアップや昇給の機会を逃してしまうことがある
2.扶養内で働く上で知るべき「年収の壁」
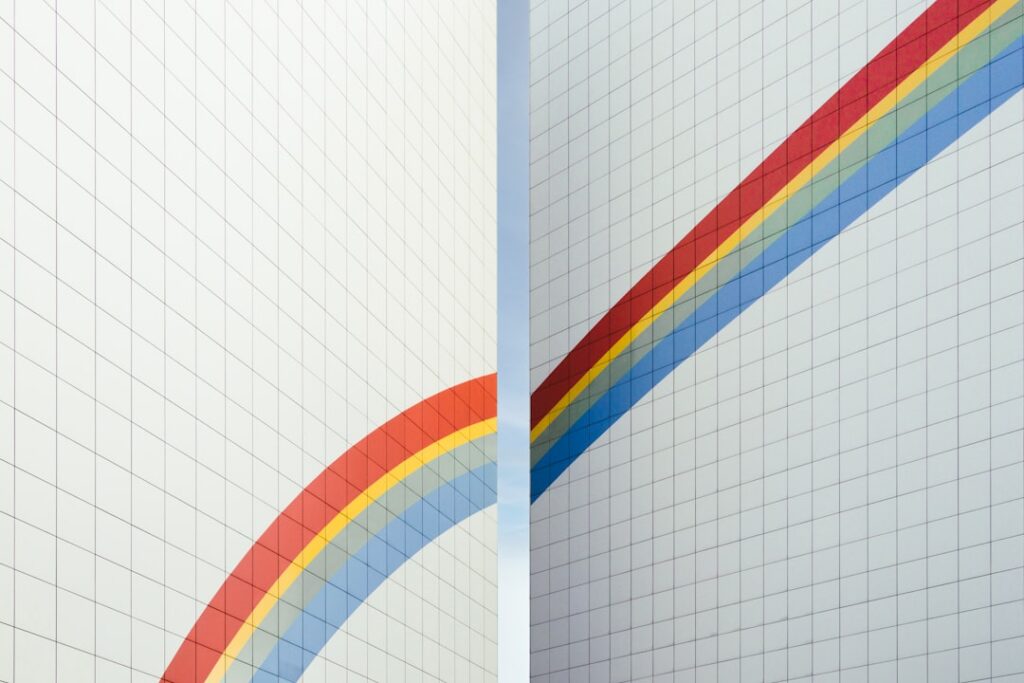
2.1.そもそも「収入」と「所得」の違いとは
「年収の壁」を理解する上で、「収入」と「所得」の違いを知ることは不可欠です。国税庁では、「収入」を給与や賞与の総支給額、「所得」を収入から給与所得控除などの必要経費を差し引いた金額と定義しています。税金の計算は「所得」を基準に行われるため、この違いを正確に把握しておきましょう。
2.2.100万円の壁 住民税の非課税限度額
給与収入が100万円を超えると、多くの自治体で住民税の支払い義務が発生します。住民税は、所得に応じて課税される「所得割」と、所得にかかわらず定額が課される「均等割」で構成されています。所得割と均等割の両方が非課税となる基準は、給与収入ベースで100万円が目安です。ただし、この非課税基準額は自治体によって異なり、特に均等割は給与収入93万円や97万円といった100万円未満のラインから課税が始まる場合があるため、実際の課税開始ラインは93万円から100万円前後で変動します。
2.3.103万円の壁 所得税がかからない上限額
給与所得控除(最低55万円)と基礎控除48万円の合計103万円は、所得税が課税されない収入の上限です。この金額を超えると、超えた分に対して所得税がかかり始めます。ただし、2025年からの税制改正により、この「年収の壁」は大きく変わります。まず、配偶者や親族の扶養に入るための年収上限(所得税上)は、これまでの103万円から123万円に引き上げられます。さらに、働く本人の所得税が非課税となる上限は、年収200万円以下の人の場合、最大160万円まで引き上げられます。
2.4.106万円の壁 社会保険加入の条件
以下の条件をすべて満たす場合、年収106万円(月収8.8万円)以上で社会保険への加入が義務付けられます。
- 従業員数51人以上の企業に勤務
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 雇用期間が2ヶ月を超える見込み
- 学生ではないこと
この壁を超えると、厚生年金と健康保険の保険料が給与から天引きされます。
2.5.130万円の壁 扶養から外れるボーダーライン
年収が130万円以上になると、原則として勤務先の従業員数にかかわらず、配偶者の社会保険の扶養から外れなければなりません。扶養から外れた後は、ご自身の勤務先の社会保険の加入要件を満たす場合はそちらに加入し、要件を満たさない場合に自身で国民年金と国民健康保険に加入して保険料を支払う必要があります。収入は過去の実績ではなく「将来の見込み額」で判断されるため、繁忙期の残業などで一時的に収入が増えた場合も扶養から外れる可能性があります。ただし、人手不足などを理由とする一時的な収入増については、事業主の証明により引き続き扶養に入れる特例措置もあります。
2.6.150万円の壁 配偶者特別控除の満額適用上限
配偶者の年収が103万円を超えても、世帯主の税負担を急に増やさないための制度が「配偶者特別控除」です。現在の制度では、配偶者の年収が150万円以下であれば、世帯主は満額(最大38万円)の控除を受けられます。年収150万円を超えると、控除額は収入に応じて段階的に減少していきます。ただし、2025年からは満額控除を受けられる年収上限が160万円に引き上げられる予定です。
2.7.201万円の壁 配偶者特別控除が適用外に
配偶者の給与収入が201.6万円を超えると、配偶者特別控除の適用は受けられなくなります。この控除がなくなることで納税者本人の税負担が増加し、また配偶者自身も収入額に応じて所得税・住民税や社会保険料の負担が発生する場合があるため、世帯全体の手取り額に大きな影響が出る可能性があります。
2.8.最新情報 制度改正と年収の壁 支援強化パッケージ
人手不足への対応と働き方の多様化を後押しするため、政府は2023年10月から「年収の壁・支援強化パッケージ」を実施しています。このパッケージには、キャリアアップ助成金の「社会保険適用時処遇改善コース」が新設され、従業員が「106万円の壁」や「130万円の壁」を超えて社会保険に加入する際に、企業が手当支給などで収入減少を補うと、国が企業に対して助成金(従業員1人あたり最大50万円)を交付します。また、繁忙期などで一時的に年収が130万円を超えた場合でも、事業主の証明があれば連続2回まで扶養に留まれる仕組みも導入されました。これにより、一時的な収入増による手取り減少を気にせず働ける環境整備が進められています。
| 壁の金額 | 対象 | 2025年時点の概要 |
|---|---|---|
| 110万円 | 住民税 | 住民税が非課税となる上限(2025年所得分から適用、自治体により変動) |
| 106万円 | 社会保険 | 一定の条件下で社会保険の加入義務が発生するライン |
| 123万円 | 所得税 | 配偶者控除が満額適用される上限(2025年改正後) |
| 130万円 | 社会保険 | 勤務先規模を問わず社会保険の扶養から外れるライン |
| 160万円 | 所得税 | 配偶者特別控除が満額適用される上限(2025年改正後) |
| 201万円 | 所得税 | 配偶者特別控除が適用されなくなるライン |
3.扶養内勤務で失敗しないための注意点と働き方
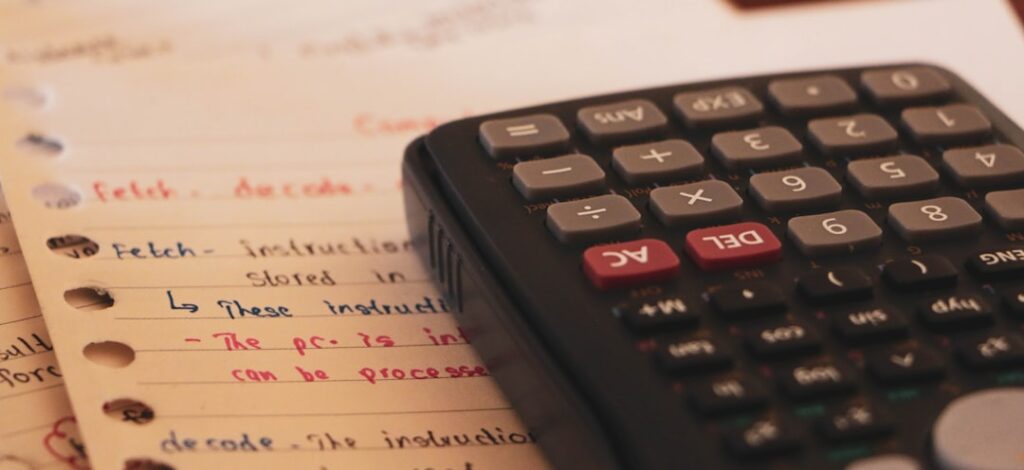
3.1.勤務時間や実務上の目安を把握する
扶養の範囲内で働くためには、自身の時給から月間の上限労働時間を計算しておくことが有効です。特に「130万円の壁(社会保険の壁)」を越えないためには、以下の計算式が目安になります。
年収上限 ÷ 12ヶ月 ÷ 時給 = 1ヶ月あたりの上限労働時間
例えば、時給1,200円で年収130万円未満を目指す場合、1ヶ月あたりの上限労働時間は約90時間(130万円 ÷ 12ヶ月 ÷ 1,200円)です。この130万円の年収には、残業代や賞与、交通費も含まれるため注意が必要です。
ただし、「年収の壁」は複数あり、従業員数などの条件によっては「106万円の壁」が適用され、130万円未満でも勤務先の社会保険への加入義務が生じることがあります。106万円の壁の計算では、月額賃金に原則として残業代・賞与・交通費は含まれません。このように制度は複雑なため、給与明細を細かく確認し、不明な点は勤務先の経理担当者に確認することが非常に重要です。
なお、政府は事業主の証明があれば一時的に年収が130万円を超えても扶養を継続できる仕組みを導入しています。
3.2.扶養内勤務が将来の年金に与える影響
扶養内で働き、国民年金の第3号被保険者である期間は、保険料を自己負担しなくても年金の受給資格期間としてカウントされます。しかし、将来受け取る老齢基礎年金の額は、保険料を納付した期間に応じて決まるため、厚生年金に加入している場合と比べて受給額は増えません。日本年金機構によると、2025年度の国民年金保険料は月額17,510円です(nenkin.go.jp)。壁を越えて厚生年金に加入すれば、この保険料負担は発生しますが、将来の老齢基礎年金に加えて報酬比例部分が上乗せされるため、長期的に見れば手厚い保障につながります。
3.3.扶養内勤務に関するよくある質問と回答
Q. 住民税の壁が自治体で違うのはなぜですか?
A. 住民税の非課税限度額は、地方税法に基づき各自治体が条例で定めているためです。お住まいの市区町村のウェブサイトで正確な金額を確認することをおすすめします。
Q. 106万円の壁の年収要件が撤廃されたらどうなりますか?
A. 厚生労働省の計画通りに進めば、将来的には週の労働時間が20時間を超えるだけで、年収にかかわらず社会保険の加入対象となる見込みです。扶養内に留まりたい場合は、労働時間を週20時間未満に調整する必要があります。
Q. パートから正社員に切り替える最適なタイミングはいつですか?
A. 子供の進学や住宅ローンの返済など、ライフステージの変化が大きなきっかけとなります。扶養内で働くメリット(税・社会保険料の負担軽減)と、正社員として働くメリット(収入増、手厚い社会保障、キャリア形成)を天秤にかけ、世帯全体の収入や将来設計を踏まえて総合的に判断することが重要です。
4.まとめ

4.1.扶養内勤務を賢く活用するためのポイント
- 税法と社会保険、2つの扶養基準を正しく理解する
- 法改正で「壁」の金額は変動するため、常に最新情報を確認する
- 目先の手取りだけでなく、将来の年金額やキャリアプランも考慮し、時には壁を越える選択も検討する
扶養内勤務は、税負担や社会保険料を抑えながら柔軟に働ける有効な選択肢です。しかし、そのルールは複雑で、法改正によって常に変化しています。「働き損」を避け、自身のライフプランに合った最適な働き方を見つけるために、この記事で解説した知識を定期的に見直し、賢い家計管理に役立ててください。
扶養内で働きたい!在宅ワークにチャレンジしてみたい!と考えている方におすすめ、リモートワークでキャリアを築くための小さな一歩を安心して踏み出せるようサポートするコミュニティ型スクール、「リモチャン!」。リモチャン!を通じて、ぜひあなたも一歩踏み出しませんか。リモチャン!公式LINEで情報発信中です。