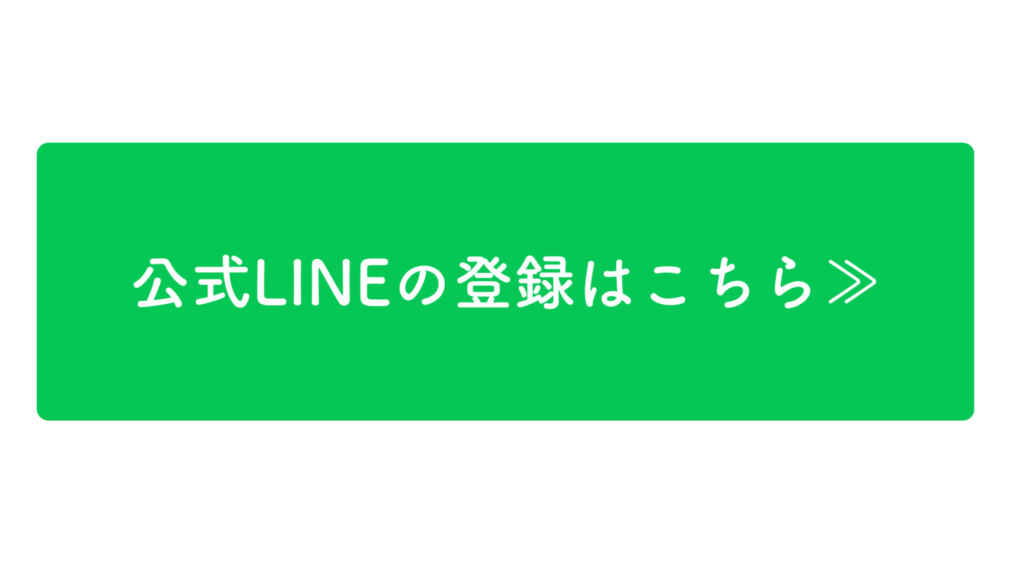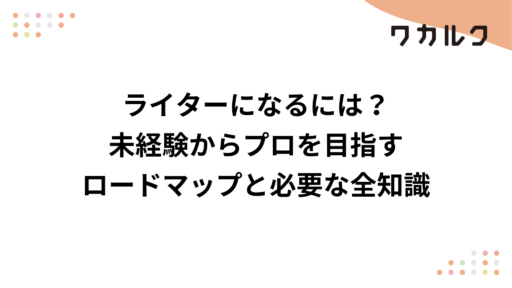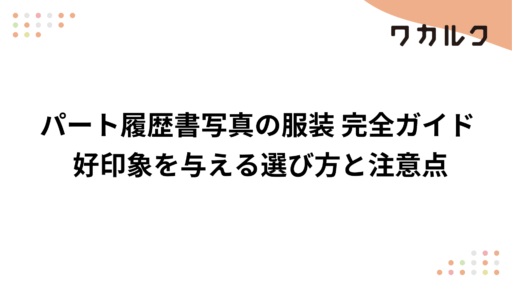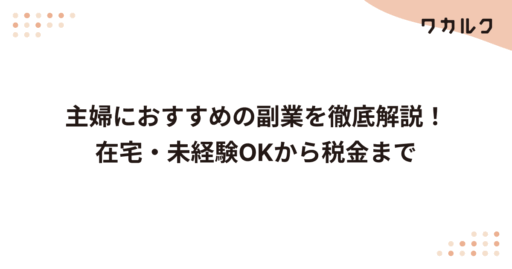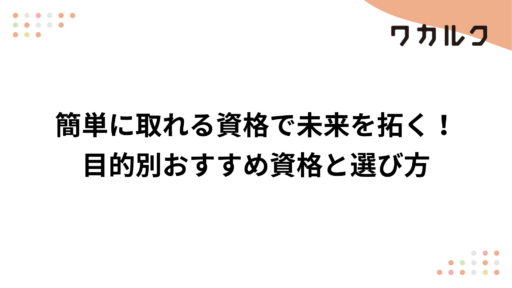
社員登用制度とは?正社員への道筋と成功のポイントを徹底解説
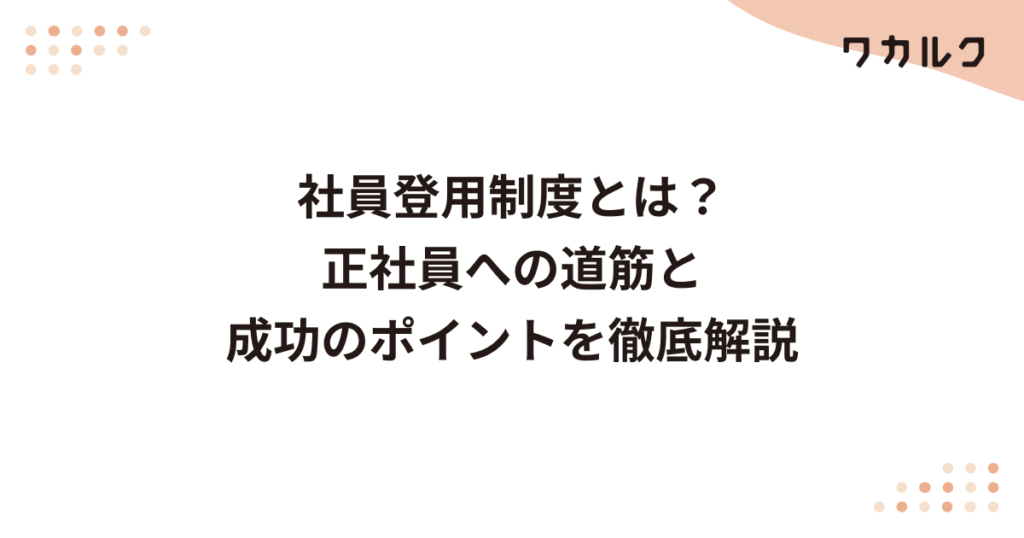
現在の職場でやりがいを感じつつも、「このまま非正規で働き続けていいのだろうか?」「もっと安定した収入やキャリアアップの機会が欲しい」といった漠然とした不安を抱えていませんか。そんなあなたにとって、慣れ親しんだ環境で正社員への道を開く「社員登用制度」は、キャリアの大きな転機となり得ます。本記事では、この制度の仕組みから、登用を成功させるための具体的なステップ、そして知っておくべきメリット・デメリットまでを網羅的に解説。あなたのキャリアプランを具体化し、着実に未来を切り拓くための羅針盤となるはずです。
目次
1.社員登用制度の基本を理解しよう

1.1.社員登用制度とは?その定義と目的
社員登用制度は、パート・アルバイト・契約社員・派遣社員などの非正規雇用から正社員へ転換できる社内制度を指します。企業が独自に設ける登用基準をクリアし、面接や筆記試験などのプロセスを経て正社員として登用される仕組みです。非正規雇用者にとっては雇用と処遇の安定が得られ、企業にとっては優秀な人材を低リスクで見極め、長期定着を図れる点が最大の目的です。
社員登用制度が注目される背景には、生産年齢人口の減少や採用難があります。日本の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少が続き、内閣府の「令和5年版高齢社会白書」によると、2022年時点で7,421万人まで落ち込んでいます(cao.go.jp)。企業が持続的に人材を確保するうえで、すでに業務を担う非正規社員の正社員化は現実的な選択肢となっているのです。
1.2.非正規雇用と正社員の違いを再確認
正社員と非正規雇用の主な違いは以下の通りです。
| 項目 | 正社員 | 非正規雇用 |
|---|---|---|
| 雇用期間 | 期間の定めなし(無期雇用) | 期間を定める契約が一般的(有期雇用) |
| 基本給 | 月給制が中心 | 時給・日給が中心(※月給制の場合もある) |
| 退職金・賞与 | 支給される企業が多数 | 支給されないケースが多い(※1) |
| 昇進・昇格 | 明確な評価制度がある | 限定的またはなし |
| 異動・転勤 | 発生する可能性が高い | 原則発生しにくい(※勤務地を限定した契約が多いため) |
【補足】
- ※1 同一労働同一賃金: 法律により、同じ企業内での正社員と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差(基本給、賞与など)は禁止されています。しかし、職務内容や責任範囲の違いなどを理由に待遇差が認められることもあり、依然として差が存在するのが現状です。
- 多様な働き方: 近年では、勤務地や職務、労働時間を限定した「限定正社員」制度など、従来の正社員と非正規雇用の中間的な働き方も増えています。
待遇面では大きな差があり、厚生労働省の「令和4年賃金構造基本統計調査」の概況でも、雇用形態別の賃金は正社員・正職員が32.8万円であるのに対し、正社員・正職員以外は22.1万円と、約10.7万円の差が報告されています(mhlw.go.jp)。
1.3.制度の導入状況と実情 どんな企業にある?
厚生労働省の労働経済動向調査によると、2024年2月時点で正社員登用制度を導入する事業所は76%に達しました。業界別では、人手不足が深刻な宿泊業、飲食サービス業や生活関連サービス業、娯楽業で特に高く、正社員化による人材定着を急ぐ企業の姿勢がうかがえます。
一方、制度があっても過去1年間に登用実績があった事業所は50%に留まり、「応募が無かった」(50%)「正社員への登用を希望する者がいなかった」(23%)といった、働き手側の意向に関する課題も浮き彫りになっています。
2.正社員登用のメリット・デメリット

2.1.正社員登用で得られるメリット
- 収入の安定と昇給のチャンス
- 健康保険、厚生年金、退職金、住宅手当など福利厚生の充実
- 社会的信用の向上により住宅ローンやクレジットカードの契約が有利に
- 職務範囲が広がり、管理職へのキャリアパスが開ける
- 社員持株会や企業年金など長期的な資産形成制度の利用が可能
実際に、公的な統計データにおいても、正社員は非正規雇用に比べて平均賃金が高い傾向にあり、正社員になることで収入の増加が期待できます。
2.2.知っておきたい正社員登用のデメリット
- 業務範囲拡大に伴う責任の増大
- 転勤・異動の辞令が出る可能性
- 時間外労働や休日出勤の増加
- 副業が制限されたり、兼業に会社の許可が必要になったりする
- 能力不足と判断された場合、試用期間後に登用が取り消しとなるリスク
自身のライフプランと照らし合わせ、メリットとデメリットを総合的に判断することが重要です。
3.正社員登用への具体的なステップ

3.1.登用基準と選考プロセス
正社員登用の一般的なフローとして、以下のようなプロセスが挙げられます。ただし、これらはあくまで一例であり、企業の規模や方針によって内容は異なります。
- 勤続年数や人事評価などの社内基準を満たした従業員が登用を申請
- 人事部による書類審査(勤務態度・実績・勤怠状況などを確認)
- 筆記試験(一般常識・適性検査など)または小論文
- 一次面接(所属部署の管理職など)と二次面接(役員・人事部長など)といった複数回の面接
- 内定通知と、正社員としての労働条件の提示
また、選考における評価指標には、以下のような要素が含まれることが多いとされています。
- 業務遂行能力と成果指標(KPI)の達成度
- コミュニケーション能力とチーム内での協調性
- 後輩への指導力やリーダーシップの発揮
- 業務に関連する資格取得や自己啓発への取り組み
3.2.登用されやすい人の特徴と行動
- 仕事の質と量の双方で高いパフォーマンスを継続的に発揮する
- 上司への報告・連絡・相談を徹底し、チーム全体の成果を最優先に考える
- 業務改善提案やDX化のアイデアを自発的に発信する
- 会社のビジョンや経営理念を深く理解し、面接で自身の貢献意欲を具体的に語れる
- 定期的なキャリア面談の場で、正社員になりたいという意欲を明確に伝える
上記の行動を継続することで、直属の上司から高い評価を得やすくなり、登用への推薦もスムーズになります。実際に、多くの企業が正社員登用の際に「これまで担当してきた仕事での実績・成果」を重視する傾向にあります。
4.よくある疑問と正社員を目指す他の方法

4.1.社員登用制度に関するよくある質問と注意点
Q.年齢制限はあるのか
A.法律により募集・採用時の年齢制限は原則禁止されているため、多くの企業は公に年齢上限を設けていません。しかし、長期的なキャリア形成を期待してポテンシャルを重視し、若年層が有利になる傾向はあります。
Q.登用試験に落ちたら再受験できるのか
A.再受験の可否や時期は企業の規定によりますが、半年から1年後に再受験の機会を設ける企業が多いです。再挑戦で合格するには、前回の不合格理由を改善し、成長を示すことが不可欠です。
Q.登用を辞退できるのか
A.登用は双方の合意に基づくため、辞退は可能です。ただし、辞退後に再申請する場合、企業によっては一定期間(例: 1〜3年程度)応募を受け付けない規定を設けていることがあるため、慎重な判断が求められます。
4.2.社員登用制度がない場合の正社員への道筋
- 転職サイトやエージェントを活用して正社員求人に応募する
- 紹介予定派遣を利用し、最長6か月の派遣期間後に双方合意の上で正社員登用を目指す
- 無期転換ルール(同一企業との有期労働契約が通算5年を超えた場合に申請可能)を適用し、無期雇用契約に切り替えたうえで社内でのキャリアアップを狙う
厚生労働省の統計等によると、紹介予定派遣で派遣期間が終了した後に派遣先で直接雇用される割合は約5〜6割で、そのうち正社員として雇用されるのは約6割とされています。これを踏まえると、紹介予定派遣から最終的に正社員になれる割合は3割前後と推定され、社員登用制度がない企業に勤めている場合の有効な選択肢となります。
5.まとめ

5.1.社員登用制度を理解し、キャリアアップを目指そう
社員登用制度は、非正規雇用者にとって正社員になる有力なステップであり、企業側にとっては優秀な人材を確保するための重要な戦略でもあります。本記事で解説したように、制度の定義・導入状況・メリットとデメリット・選考プロセス・成功のポイントを把握し、自身のキャリアプランに沿った行動を取ることで、登用成功の可能性は大きく高まります。
正社員化はゴールではなく、新たなキャリアのスタートです。主体的に学び続け、自らの市場価値を高める姿勢こそが、長期的なキャリアアップにつながるでしょう。厚生労働省も「キャリアアップ助成金」などを通じて企業による非正規雇用労働者のキャリアアップを支援しており、国全体としても個人の主体的なキャリア形成を後押しする動きが加速しています。
リモートワークで働きたい方におすすめ、リモートワークでキャリアを築くための小さな一歩を安心して踏み出せるようサポートするコミュニティ型スクール、「リモチャン!」。リモチャン!を通じて、ぜひあなたも一歩踏み出しませんか。リモチャン!公式LINEで情報発信中です。