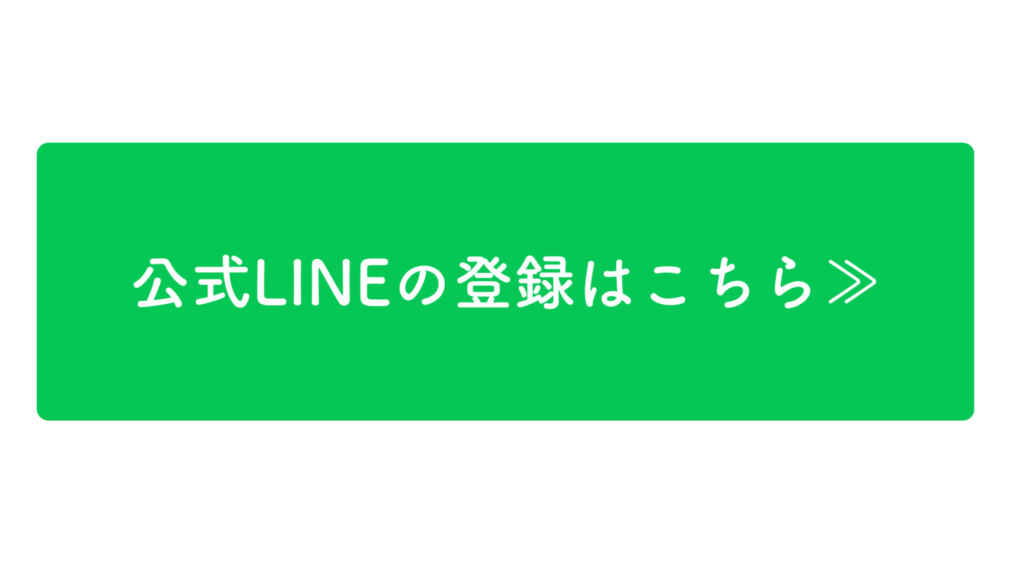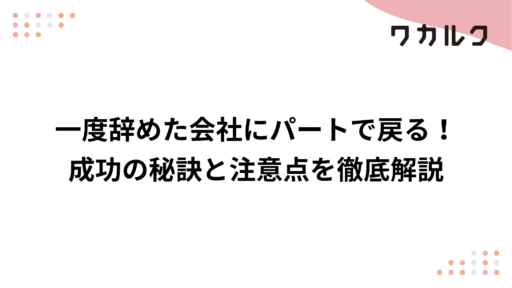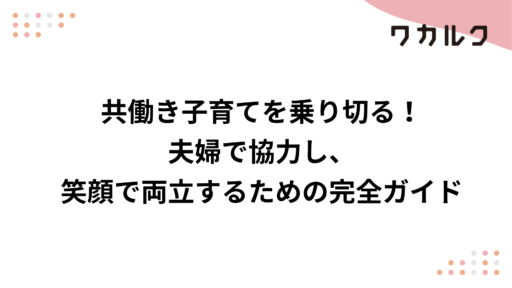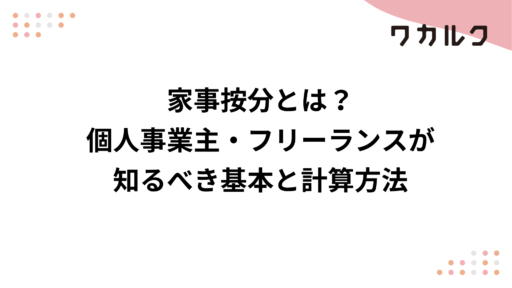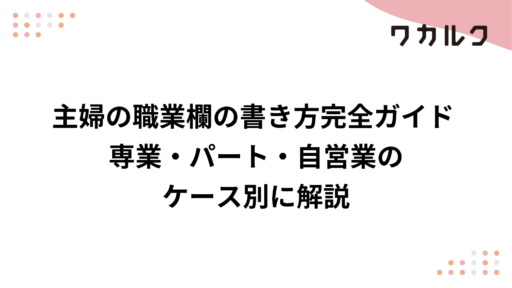
慣らし保育と育休を徹底解説!給付金・復職・延長の疑問を解消
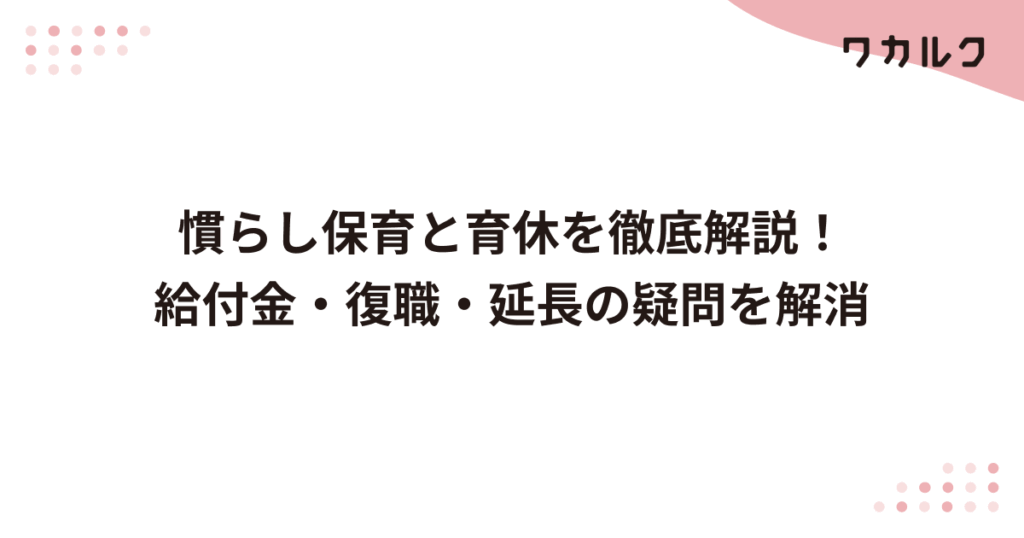
育休からの復職を目前に控え、いよいよ始まる保育園生活。しかし、その第一関門となる「慣らし保育」に、多くの親が不安を感じています。「子どもは新しい環境に馴染めるだろうか」「仕事との両立はうまくいくのか」「この期間、育休給付金はどうなるの?」――こうした疑問や心配は尽きません。この記事では、そんな慣らし保育期間を親子で安心して乗り越えるための具体的な知識とノウハウを、育休制度や給付金のルールと絡めて徹底解説します。読み終える頃には、漠然とした不安が解消され、自信を持って仕事と育児の両立に向けた第一歩を踏み出せるようになっているはずです。
目次
1.慣らし保育の基本を知ろう
1.1.慣らし保育とは?その目的と必要性
慣らし保育とは、保育園に入園したばかりの子どもが環境の変化に少しずつ慣れるため、登園時間を段階的に延ばしていくプロセスです。多くの自治体や園が導入しており、厚生労働省の通知でも慣らし保育の期間は「1~2週間程度が適当」とされています。実際に、長崎市が2024年に公表した市民からの提案への回答でも、週明けから6日間を基本とする運用が示されました。一般的に、環境の変化は子どもの睡眠や食欲に一時的な影響を与えることがあるため、慣らし保育はこうした心身のストレス反応を緩やかにするための重要なプロセスとされています。
目的は大きく三つあります。
- 子どもの生理的リズムを園生活に合わせる
- 保育士が子どもの性格や体調を把握する
- 親が送迎やコミュニケーションに慣れる
こうした目的を意識すると、「早くフルタイムで預けたい」という焦りが和らぎ、計画的なスケジュールを立てやすくなります。
1.2.慣らし保育の一般的な期間とスケジュール
ある民間調査では、慣らし保育が7日以上と回答した保護者が68%を占め、11〜14日が最多という結果が出ています(prtimes.jp)。実務上は以下の流れが一般的です。
- 1~2日目
登園1~2時間、室内遊びのみ
- 3~4日目
午前のおやつと給食を園で経験
- 5~7日目
昼寝まで体験し、午後3時前後に降園
- 8日目以降
おやつ後まで延長し、最終的に夕方まで過ごす
年齢が上がるほど適応は早く、2歳児以上では1週間未満で終える園もあります。逆に生後6か月未満の低月齢児は、授乳間隔や昼寝リズムの違いから2週間以上かけるケースが少なくありません。
1.3.慣らし保育でよくある課題と対処法
泣き止まない、食事を拒む、昼寝が短いなどの課題は珍しくありません。保育の専門家によると、これらの行動は「分離不安」の現れであることが多く、親との愛着関係がしっかり形成されている証拠でもあります。対処の基本は「家庭と園で生活リズムをそろえる」ことです。
- 泣き止まない場合
前夜の入眠を早め、朝食後すぐの登園で体力を温存
- 食事が進まない場合
自宅で献立に近い食材や味付けを練習
- 昼寝ができない場合
休日も園と同じ時間に横になる習慣を作る
- 体調を崩しやすい場合
登園前後の手洗いと水分補給を徹底
親が情緒不安定になることも多いため、園だよりや連絡帳を活用し、気になる点を早めに相談すると安心です。
慣らし保育中の方におすすめ、リモートワークでキャリアを築くための小さな一歩を安心して踏み出せるようサポートするコミュニティ型スクール、「リモチャン!」。リモチャン!を通じて、ぜひあなたも一歩踏み出しませんか。リモチャン!公式LINEで情報発信中です。
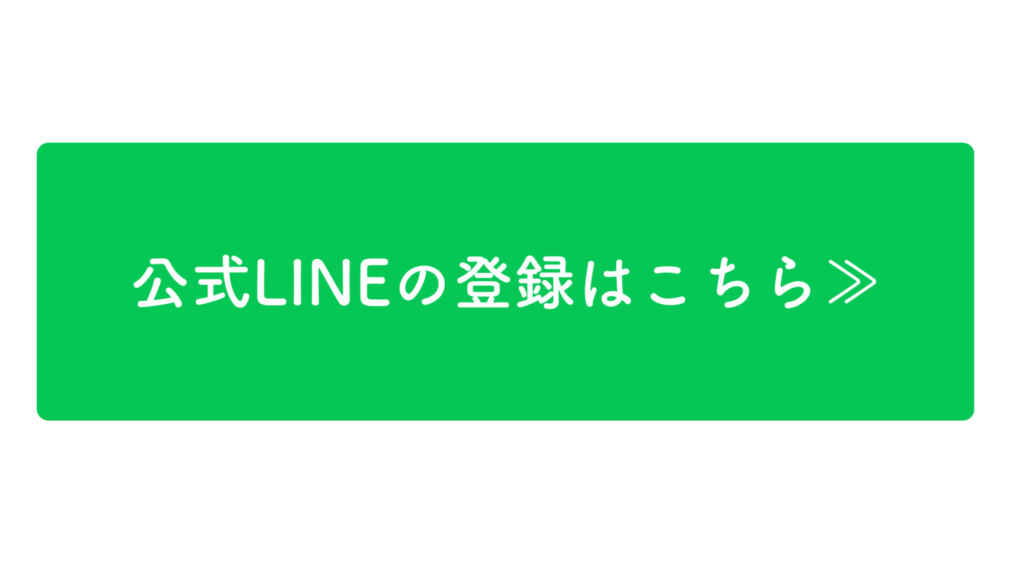
2.育児休業給付金と慣らし保育のリアル

2.1.慣らし保育期間中の育児休業給付金はどうなる?
育児休業給付金は、雇用保険法に定められた制度であり、育児に専念する労働者の生活を支えることを目的としています。支給額は、育児休業開始から180日目までは休業開始前賃金の67%、以降は50%です。慣らし保育で一日数時間の登園を始めても、就労実態がない限り「休業中」とみなされるため支給は継続されます。ただし日単位や時間単位で就労し賃金が発生すると、賃金額によっては給付額が減額されるので注意が必要です。
申請の流れは次のとおりです。
- 初回の申請では、会社が「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」と「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」をハローワークに提出します。
- 2回目以降は、2か月ごとに育児休業給付金支給申請書を提出します(多くは会社経由で行います)。
- 休業中に就労した場合は、賃金台帳や出勤簿など、就労日数や賃金額を証明できる書類を添付します。
2.2.慣らし保育中に一歳を過ぎた場合の給付金
原則として給付金は一歳の前日で終了しますが、保育所に入所できないなど一定の要件を満たすと一歳六か月まで延長できます。2025年4月からは、延長申請時に職場復帰の意思などを確認するための申告書等の提出が追加で必要になります。慣らし保育中であっても、実際に入所できていれば「保育所に入所できない」要件を満たさないため延長できません。延長を視野に入れる場合は、自治体が発行する「入所保留通知書」を確実に取得しておきましょう。
2.3.育休延長は慣らし保育を理由にできる?注意点も解説
育児・介護休業法上、慣らし保育そのものは育休延長の事由に該当しません。ただし、特定の状況下では延長が認められる可能性があります。例えば、保育所の内定を転居など客観的にやむを得ない理由で辞退し、再度待機児童となった場合などです。
子ども本人の疾病については直接の延長事由として明記されていませんが、状況によっては個別に判断されることがあります。
一方で、「慣らし保育に付き添いたい」「子どもの情緒が不安」といった個人的な理由は、法律が定める延長要件には合致しません。
2025年4月から施行される改正育児・介護休業法では、企業に柔軟な働き方への配慮が求められるため、在宅勤務や短時間勤務制度などを活用して慣らし保育に対応する選択肢が広がります。
3.慣らし保育と復職をスムーズに進めるには

3.1.慣らし保育期間中の収入はどうなる?
慣らし保育期間中も育児休業扱いであれば給付金が支給されるため、復職まで手取りで休業前の8割程度を確保できます。2025年度から開始予定の出生後休業支援給付と組み合わせると、条件によっては最大で手取り10割相当になるケースもあります。一方、時短勤務で復職すると給与が減るため、月額総収入は育児休業給付金を受給している場合より低くなることが多いです。家計シミュレーションを行い、復職月の社会保険料や住民税の変動も確認しておくと安心です。
3.2.慣らし保育と復職のベストなタイミング
復職日は園の慣らし保育最終日から少なくとも2日後に設定すると、突然の発熱等に備えられます。特に4月入園では、復職期限を5月1日や10日とする自治体が多く、ゴールデンウィークが重なる点も要確認です。会社との調整では、
- 復職予定日の1か月前までに正式申請
- 慣らし保育の進捗を週次で共有
- 在宅勤務可否や残業免除の取り扱いを確認
がポイントになります。
3.3.復職に向けた準備と相談先
- 会社の人事担当者
就業規則と勤怠システムの確認
- 上司
業務分担と時差出勤の可否を相談
- 配偶者や家族
送迎分担表を作成し、急病時の連絡フローを決定
- 自治体子育て支援窓口
一時預かりやファミリーサポート登録を早めに実施
専門機関として、地域の「こども家庭センター」(旧:子育て世代包括支援センター)や社会保険労務士への個別相談も有効です。特に、母子保健法に基づき各市町村に設置されているこども家庭センターでは、保健師や助産師が常駐し、育児に関するあらゆる相談に無料で応じてくれます。
3.4.慣らし保育をサポートするサービスを活用しよう
| サービス | 主な内容 | 料金目安 |
|---|---|---|
| ベビーシッター | 登園付き添い、送迎代行 | 1時間2,000円前後+交通費 |
| 一時預かり | 市区町村や園が実施、保育短時間枠 | 1日2,000円〜4,000円 |
| ファミリーサポート | 地域ボランティアによる送迎や預かり | 1時間800円〜1,200円 |
| 病児保育 | 医師常駐施設で体調不良児を預かり | 1日2,000円〜3,000円程度(※自治体施設の場合。訪問型などは料金が異なることがあります) |
慣らし保育をスムーズに始めるために、入園申し込みなどの手続きは事前に済ませておくと安心です。
4.まとめ
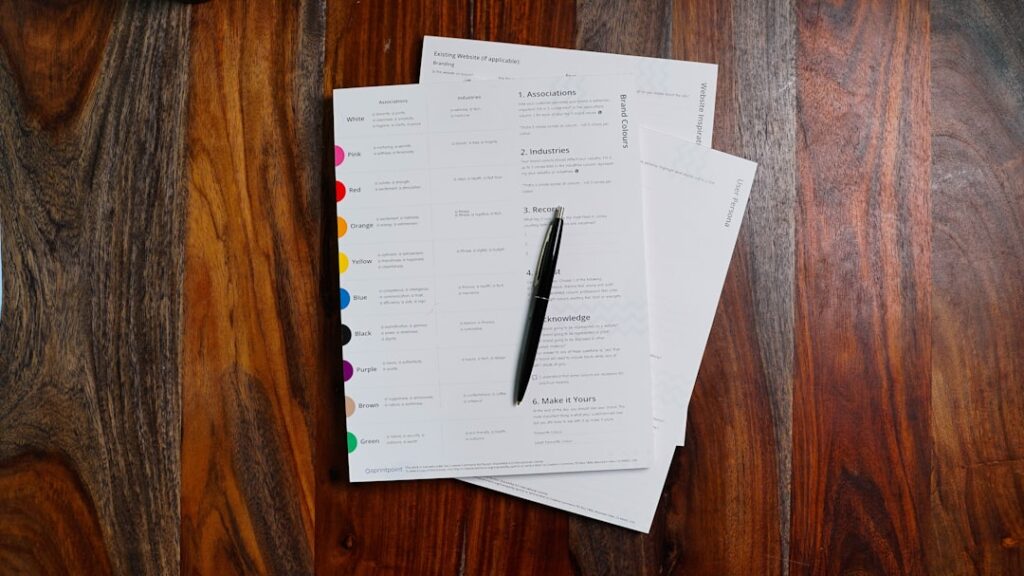
4.1.慣らし保育と育休のポイント
- 慣らし保育は1~2週間が目安だが、子どもの個性で前後する
- 給付金は慣らし保育中も原則支給されるが、就労時間発生で減額リスクあり
- 一歳を迎える場合は入所保留通知書と職場復帰意思の申立書が延長の鍵
- 改正育児・介護休業法により2025年4月以降は企業の働き方配慮義務が拡大
- 復職日は慣らし保育終了後2日以上あけ、家族と送迎体制を共有
本記事を参考に、余裕をもったスケジュールで慣らし保育と復職準備を進めれば、仕事と育児の両立がよりスムーズになるでしょう。
育休中の方やこれから復帰したいと考えている方におすすめ、リモートワークでキャリアを築くための小さな一歩を安心して踏み出せるようサポートするコミュニティ型スクール、「リモチャン!」。リモチャン!を通じて、ぜひあなたも一歩踏み出しませんか。リモチャン!公式LINEで情報発信中です。