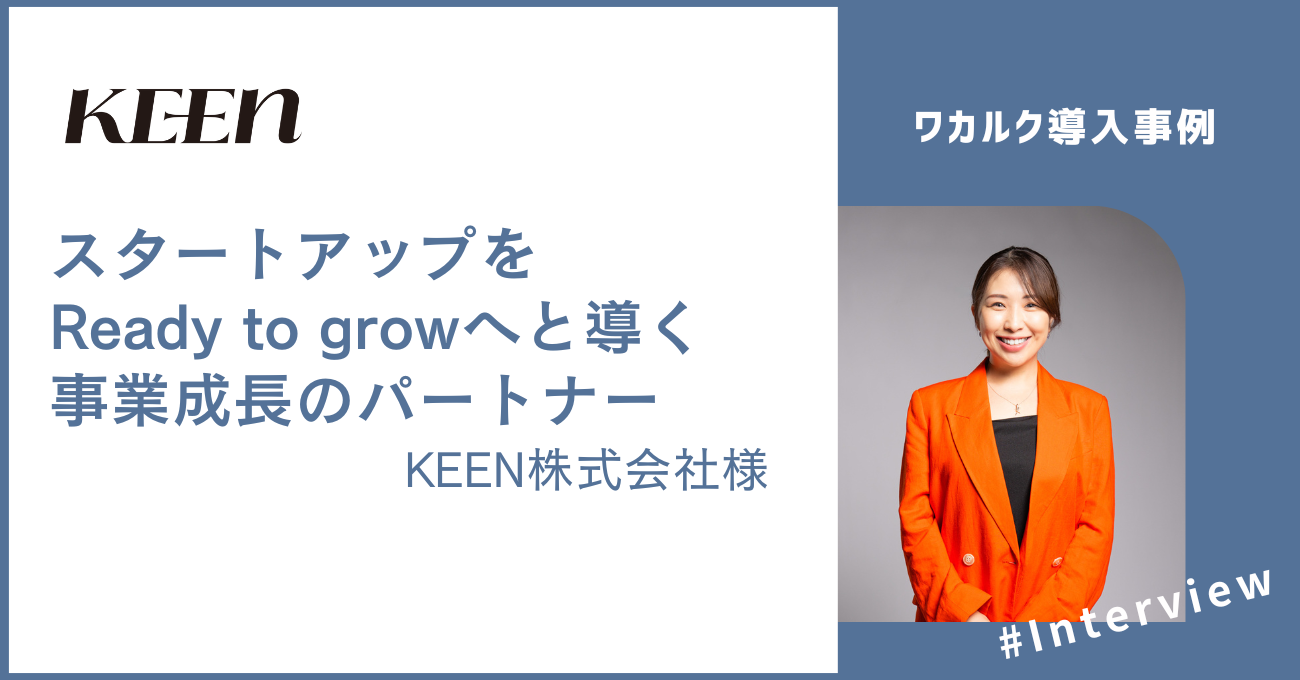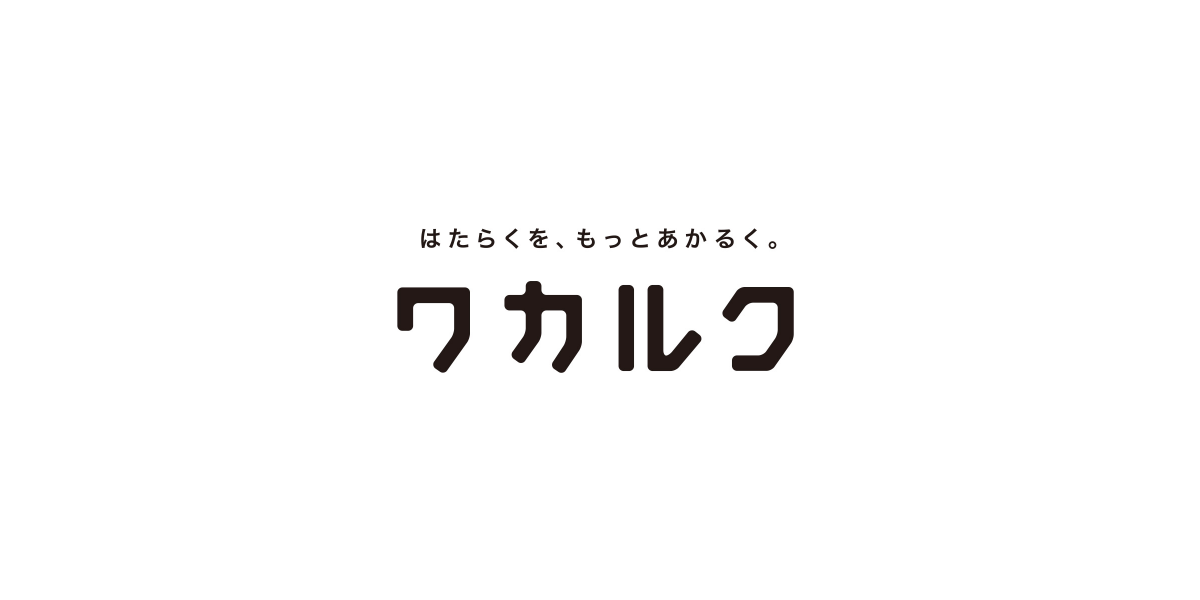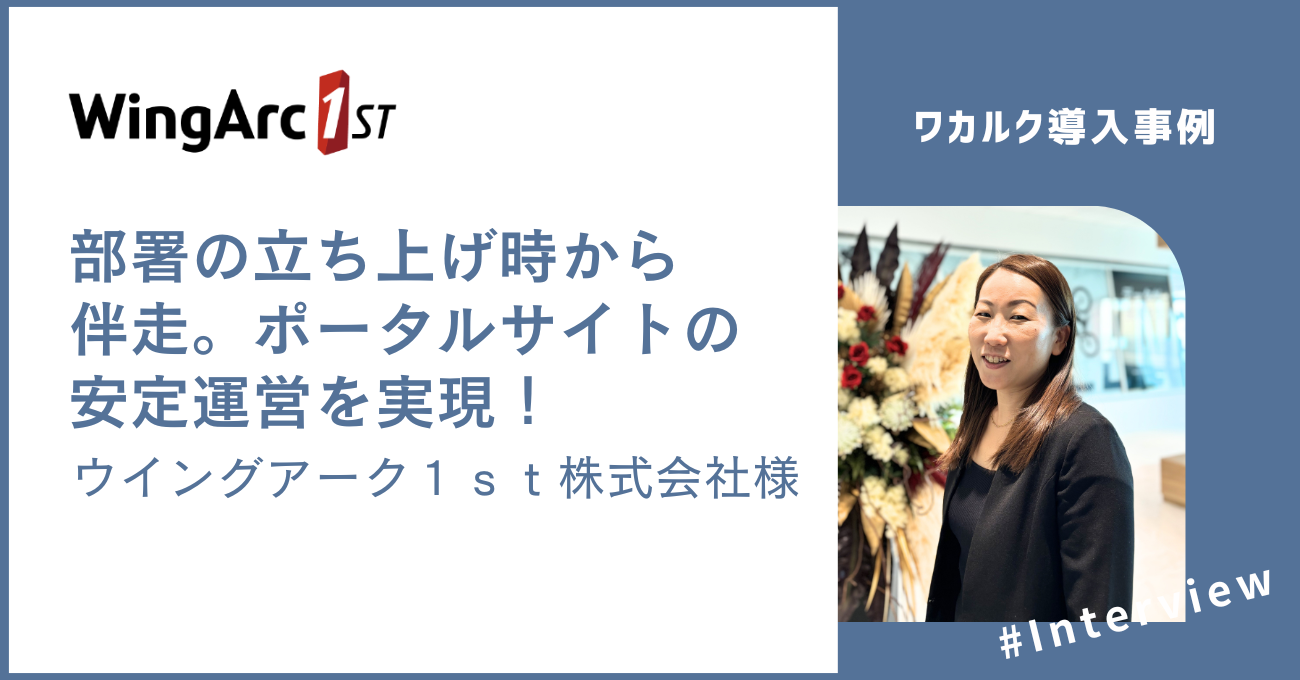を徹底解説-512x288.png)
2025年育児・介護休業法改正!企業が準備すべきことは?
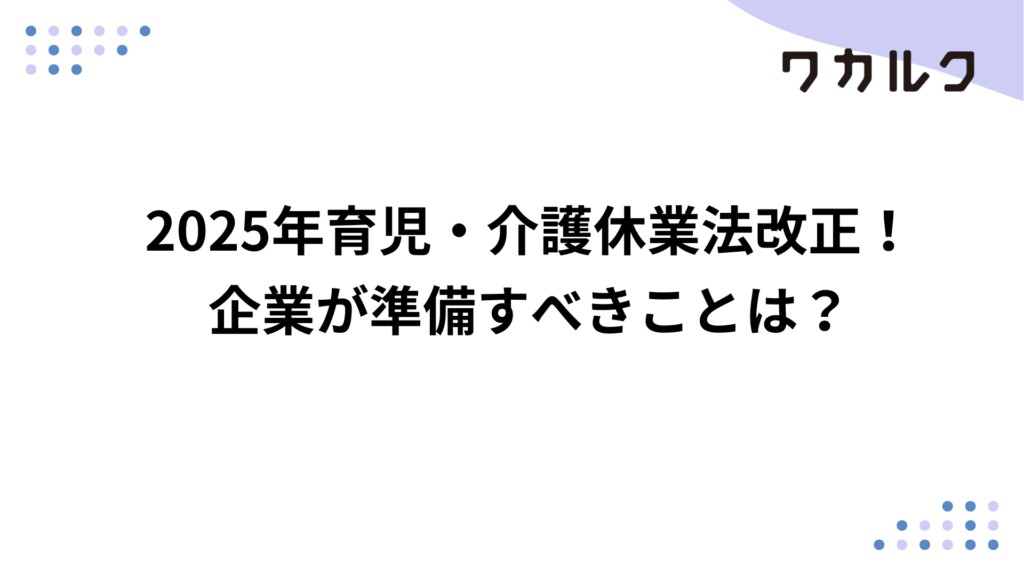
目次
はじめに:2025年の育児・介護休業法改正の概要
2025年4月と10月の2段階で施行され、各段階で企業は対応する必要があります。育児休業法改正・介護休業法改正は、従業員が育児や介護を理由に安心して働き続けられる環境を作り出す上で大きな転機となります。
小学校就学前の子を持つ従業員に対する残業免除の対象拡大、子の看護休暇の取得範囲見直し、テレワーク導入の努力義務などが含まれます。
これらの変更点によって「育児と仕事の両立」「介護離職防止」を実現するための制度が充実し、働く人々のライフステージに合わせた柔軟な勤務が可能になります。 また、育児休業取得率を引き上げるために、企業規模によっては男性の育児休業取得にも積極的に取り組むことが求められ、特に従業員300名を超える会社では育児休業公表義務が強化されます。
こうした措置は企業の社会的責任を果たすのみならず、多様な人材を確保する戦略としても有効です。 この記事では、改正内容が企業に与える影響と、どのような準備を進めれば良いのかを中学生でも理解しやすい言葉を使いながら、実践的な例とともに解説していきます。今後の働き方改革をはじめ、社会全体の意識変化が加速する中で、企業が対応を誤ると大きなリスクを負う可能性もあります。ぜひ、本記事を参考に組織の労働環境を整備し、ワークライフバランスを高める取り組みを進めてください。
1. 改正の主なポイントと企業への影響
2025年に施行される育児休業法改正や介護休業法改正には、大きく分けて五つの柱があります。まずは、2025年4月1日からの施行で企業に求められている点を整理しましょう。
残業免除の対象拡大では、3歳未満の子を育てる従業員だけでなく、小学校就学前の子を持つ従業員まで請求できるように範囲が拡大されます。次に、子の看護休暇の取得年齢が高まることや取得理由が広がる点も注目すべき変更です。
さらに、テレワークの導入が努力義務として明文化され、企業は働く場所を選択しやすい環境を整えなくてはいけません。同時に、育児休業取得率を改善すべく、ある一定規模以上の会社には育児休業の取得情報公表が求められます。そして、介護離職防止を目的とした新制度も追加され、企業は複数の選択肢から支援策を選択することが必要になります。
以下では、これらの改正ポイントを一つひとつ詳しく見て、具体的な影響やリスク、そして実務面での注意事項を解説します。
1.1. 残業免除の対象拡大とその影響
これまでの残業免除は、3歳未満の子を養育する従業員が対象でしたが、改正後は小学校就学前の子を持つ社員も残業を免除できるようになります。
この変更によって、企業側は勤務体制やシフトの組み方を見直し、労働時間の制限が増える方々に配慮する必要が出てきます。たとえば、フレックスタイム制度や時差出勤を活用して、育児中の社員が業務を整理しながら働けるような計画を立てることが重要です。
また、残業免除を活用する社員とそうでない社員の業務バランスを取るため、仕事の割り振りや担当者の配置を再検討する必要もあります。急な対応が増えると、他のメンバーに負担が集中し、人間関係やモチベーション低下のリスクが高まるからです。
結果的に、残業免除をきっかけとして「育児と仕事の両立」を前向きに考える機会を創出できれば、従業員同士の助け合いが促進され、組織全体の結束力向上や人材流出の防止につながるでしょう。
1.2. 子の看護等休暇の拡充と新たな取得理由
小学校就学前までだった子の看護休暇の対象が小学校3年生修了まで拡大されるため、子育て中の社員はより長い期間、柔軟に休暇を取りやすくなります。
加えて、感染症対策として学級閉鎖になった場合や、学校行事への参加といった多様な理由で休暇を取得できるよう制度が見直されました。企業は制度の詳細を従業員に周知するだけでなく、実際に「時間単位休暇」を導入するなどの運用を検討する必要があります。
具体的には、業務フローを単位ごとに整理し、数時間単位での休暇取得に対応できるよう調整することが欠かせません。また、子育て支援の視点から、休暇取得者の業務をカバーできる後方支援の仕組みを整えることも、企業が取り組むべきポイントでしょう。
以上のような拡充は、育児支援政策としてのインパクトが大きく、職場全体で協力しやすい社風を育むと同時に、企業イメージ向上も期待できる改正といえます。
1.3. テレワーク導入の努力義務と企業の対応
3歳未満の子や要介護状態の家族を抱える従業員に対して、テレワークを選択肢として提供することが努力義務化されます。これにより、家族介護支援や出産直後の子育て環境を整えやすくなると期待されています。
まず検討すべきは、社内インフラの整備です。業務上重要な情報のセキュリティ対策、オンライン会議ツールの導入、リモートでのコミュニケーションガイドライン策定などを整える必要があります。導入するだけでなく、従業員が遠隔で問題なく働ける運用マニュアルを作り、技術的サポートをいつでも受けられる体制も重要です。
さらに、勤務地の柔軟性を向上するための規程をつくり、必要に応じて社内手続きを簡略化します。たとえば、承認フローや勤務報告のルールをオンライン化し、手早く申請が行えるように工夫することが求められます。
テレワーク導入は働き方改革の一環であり、ワークライフバランスと生産性の両立を目指す企業にとっては欠かせない対応策といえるでしょう。
1.4. 育児休業取得状況の公表義務と透明性向上
従業員300名を超える企業を中心として、育児休業取得率の公表が義務化されます。男性の育児休業取得率も明確に示す必要があるため、企業の取り組みが可視化され、社内外からの注目がさらに高まるでしょう。
この公表義務は、企業が実施している両立支援制度の利用状況を公開する機会でもあります。具体的に、会社のウェブサイトや厚生労働省の専用サイトで公表する企業が増えると考えられます。より高い取得率を示すには、企業風土や上長の理解、そして部署間の協力体制なども整えておくことが大切です。
公表された育児休業取得率は、求職者にとっては企業選びの重要な指標であり、ブランドイメージの向上や人材確保につながります。結果として、ライバル企業との格差が広がる恐れもありますが、それを逆に差別化のチャンスと捉える動きが多くの企業で活発化すると考えられます。
以上の点を踏まえると、育児休業公表義務は企業の社会的責任を果たすだけでなく、新しい人材戦略を構築するきっかけにもなるといえます。
1.5. 介護に関する新たな支援制度と企業の選択
高齢化が進む現在、介護離職防止は多くの企業にとって喫緊の課題です。そのため、改正法では介護を巡る新たな支援制度が追加され、企業は選択制で対応策を導入することが求められます。
具体的には、フレックスタイム制や時差出勤による勤務条件の調整、休暇制度の拡充、ベビーシッター補助のような家族介護支援策を組み合わせて行うケースが考えられます。自社の労働者構成や事業内容に合わせて、できるだけ使いやすい選択肢を用意することが大切です。
また、個別の事情を丁寧にヒアリングして、介護中の従業員が抱える問題に合わせたカスタマイズを行うことも求められます。制度が整備されても、それを使わない環境では意味がありません。
こうした介護支援政策を導入することで、社員のモチベーション維持や離職予防が実現し、企業全体の持続的な発展につながります。
2. 具体的な対応策と企業の準備
ここからは、改正法施行に向けて企業が進めるべき具体的なステップについてお話しします。
まずはすぐに取り掛かるべきなのが、社内規程の見直しや設定です。残業免除のステップや取得手順、テレワークルールの詳細を明文化し、企業内ポータルや従業員ハンドブックに掲載するといった形で明確に示す必要があります。
次に、社員とのコミュニケーション方法を見直して、情報の漏れや意図の食い違いを防ぐ仕組みを作りましょう。特に、上司が過剰な残業を命じたり、テレワーク希望者と意思疎通がうまくいかないとトラブルの種になるので、定期的な説明会や個別ミーティングを行うと効果的です。
加えて、従業員のワークライフバランスを改善する姿勢を、全社的に共有する取り組みが不可欠です。リーダー含む管理職が率先して制度を使いこなす事例を積み重ねることで、周囲の理解と実行力が高まります。
2.1. 対応策①:育児支援のための制度選択
3歳以上小学校就学前までの子を育てる従業員に対しては、企業側が複数の支援策から最低2つを選択して導入することが求められます。
具体例としては、短時間勤務制度や保育施設設置(あるいはその費用の一部補助)などが挙げられます。また、フレックスタイム制度や時差出勤によって働く時間帯を調整する方法、テレワーク導入による在宅勤務の実施も有効です。
ただし、制度を作るだけでは不十分であり、使いやすさを保証しないと効果が半減します。たとえば、短時間勤務制度を利用すると昇進しづらいと感じられては意味がありません。そのため、評価方法の見直しや業務効率化を同時に進める必要があります。
そうした制度は、男性の育児休業や子育て支援とも連動して、社内全体のキャリア形成をサポートする重要な役割を果たします。
2.2.対応策②:周知・意向確認の方法
企業は従業員に対し、概ね制度利用対象となる時期が近づいた段階で、個別に周知と意向確認を行わなければなりません。面談や書面交付、FAX、電子メールなどの多様な方法から選び、相手に合った手段で情報を伝えることがポイントです。
このように柔軟な情報伝達手段を組み合わせることで、育児休業や介護休業を必要とする社員が手続きに関して不安にならないように配慮できます。また、周知の際には「利用者の声」や実際に制度を活用している先行事例を紹介すると、イメージを持ちやすくなります。
さらに大事なのは、法改正や社内制度自体を丁寧に説明するだけでなく、本人の家庭状況と業務内容をすり合わせることです。特に、育児と仕事の両立を希望する社員に対しては、時間単位休暇をどう使うか、どんな条件でフレックスタイムを活用できるかを詳しく説明すると安心感が高まります。
この周知・意向確認を「形だけ」の作業にしないよう、互いの意思疎通を丁寧に行い、企業文化そのものを改善する機会にしましょう。
2.3.対応策③:個別の意向聴取の実施
本人や配偶者の妊娠・出産が明らかになった段階や、子が3歳の誕生日を迎える1か月前までの間など、個別に意向を聴取するタイミングが複数設定されています。
まず、従業員が希望する勤務時間帯(始業・終業)や勤務地、両立支援制度の利用期間をしっかり聞いて、可能な限り今後の働き方を尊重できるように調整していきます。個人の置かれた家族状況が違えば、必要なサポートも異なるので、画一的に制度適用するだけではカバーしきれないケースも出てきます。
意向聴取を行う担当部署や担当者には、法知識だけでなく、コミュニケーション能力も求められます。特に、トップダウンではなく本人の意向を尊重するチームづくりが成功のカギです。職場の雰囲気づくりもあわせて検討するとよいでしょう。
こうした丁寧な聴取プロセスによって、育児休業や介護支援制度をスムーズに利用できる環境を作り出し、結果として従業員満足度と企業の生産性向上を同時に達成できる可能性が高まります。
2.4.対応策④:勤務条件の柔軟な調整
デスクワーク中心の職場であっても、介護や育児に追われると残業が厳しくなるケースが多くあります。そこで、時短勤務やフレックスタイム制度などを使い、就業時間をスライドさせる取り組みを行うと、負担を大きく減らせます。
一方で工場や店舗などの現場の場合は、ある程度シフトを組んだり、担当業務をローテーションさせる形で調整する工夫が必要です。そうすることで、小規模部門でも突然の休暇取得に対応できる柔軟性を確保できます。
勤務場所の柔軟性にも注目が集まっています。できる業務をテレワーク化したり、一部リモート研修へ変更することで、家庭と仕事の両立をサポートする動きも出てきています。こうした試みは、企業のイメージアップにも直結します。
結果として、勤務条件の多様化を実施することで、従業員が将来のキャリアをあきらめずに働き続けられる組織作りが実現し、人材の確保と定着へとつながるでしょう。
3. 法改正による企業文化とブランドイメージの変化
2025年の育児休業法改正と介護休業法改正は、単なる法律遵守の枠を超え、企業文化やブランド力を大きく変革する力を持っています。
企業が両立支援制度を整え運用を積極化することで、従業員が抱える家庭の悩みに寄り添う姿勢を示すことができます。これは、社内の人間関係や職場満足度に好影響を与え、働きやすい職場としての評判にもつながるでしょう。
また、育児・介護をサポートする環境が整った企業は、優秀な人材から選ばれやすくなり、長期的に見ても利益が大きくなる傾向が見込まれます。ライバル企業との差別化を図れるだけでなく、社会的にもポジティブな評価を得る可能性が高まります。
この章では、ワークライフバランスの向上や人材確保など、企業文化やブランドイメージがどのように変化していくかを詳しく解説します。
3.1. ワークライフバランスの改善と従業員満足度
育児や介護のために制度を活用できる環境が当たり前になると、働く人の生活リズムには大きな余裕が生まれます。
具体的な例を挙げると、小学校就学前の子を持つ社員が残業免除や子の看護休暇を使い、時間単位休暇で細かい予定を調整しやすくなると、仕事と家庭のストレスが軽減されます。これをきっかけに、職場内のコミュニケーションが増えたり、助け合いの気風が根付くことが期待されます。
結果として、従業員満足度が高まり、チーム全体のモチベーションが向上します。高いモチベーションは業務効率化やイノベーションにもつながり、企業としても収益拡大や業績向上につながる好循環を生み出します。
企業のトップや管理部門は、この好循環を意識的に促進するため、積極的に施策を打ち出し、周囲に浸透させる努力を怠らないことが重要です。
3.2. 人材の確保と定着を促進する企業文化の構築
育児・介護支援制度を適切に運用することで、社内に安心感が生まれ、優秀な人材が離職しづらい環境が整います。特に、今後の労働市場では柔軟な働き方を重視する傾向が強まるため、子育て世代はもちろん、将来の介護リスクを考慮するミドル層にも魅力的です。
こうした両立支援制度は、企業ブランドや採用活動にも直結します。就職・転職市場において、ワークライフバランスが取れる企業は「働き方改革」の先端をいく存在とアピールでき、求職者の好感度も上がるでしょう。
また、従業員50名以上規模の企業では制度整備の難しさを感じるかもしれませんが、逆に各部署の分業体制が整っていることを生かし、柔軟な働き方を展開できる強みもあります。効率よく業務を配分すれば、男女を問わずキャリア継続が期待できる組織文化が育つのです。
結果として、人材の確保と定着を促進し、長期にわたり企業価値を高めることがこの法改正の狙いとも言えます。
3.3. 社会的責任と企業倫理の実践
従業員のライフステージに配慮した施策を積極的に導入することは、企業の社会的責任を果たすうえでも重要です。特に介護支援政策の拡充によって、家族介護が必要な社員の離職を防ぐことは、組織維持の観点だけでなく、社会全体の福祉にも貢献する取り組みとなります。
企業倫理の側面から見ても、働く人たちの多様な事情を尊重する姿勢は、株主や顧客からの信頼を得る要因になります。ダイバーシティを含むESG投資の観点からも評価が高まるため、長期的な経営戦略においてもプラスに働きます。
また、外部評価だけでなく、社内においても「企業が自分たちを大切にしている」と実感すれば、従業員一人ひとりが会社を応援し、応じてパフォーマンスを高める効果があります。これはまさに、企業のブランド価値を内外で高める要素といえます。
このように、育児・介護休業法改正への対応は、経営者にとって単なる法令遵守にとどまらず、企業理念を実践する大きなチャンスなのです。
4. 2025年の法改正を企業がチャンスと捉える理由
2025年の育児休業法改正、介護休業法改正は、従業員の育児休業取得率を高めるだけでなく、時間単位休暇やテレワーク導入の促進など、実践的な働き方改革を後押しする内容が多数含まれています。
企業としては、まず法令を遵守して労働時間の制限や両立支援制度の整備を確実に行い、理念として掲げるだけでなく、実際の運用で従業員の生活を支える必要があります。この過程で蓄積されたノウハウは、競合他社と差別化する強力なアピールポイントにもなるでしょう。
さらに、介護離職防止や育児と仕事の両立を支援できれば、企業文化が大幅に向上し、人材確保が容易になります。リモートワークや時差出勤など、多様な勤務条件の調整を進めることで、従業員満足度と生産性を同時に高められる可能性が大いにあります。
法改正への対応をコスト負担だけで捉えるのではなく、組織力強化とブランドイメージ向上のチャンスと理解し、戦略的かつ柔軟に取り組むことで、企業として一段上の成長につなげていくことができます。