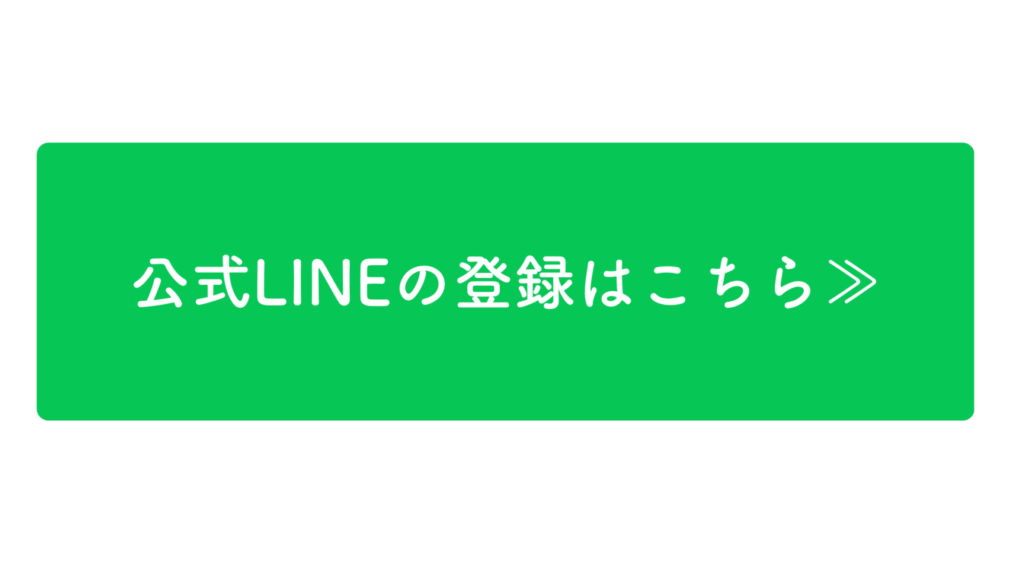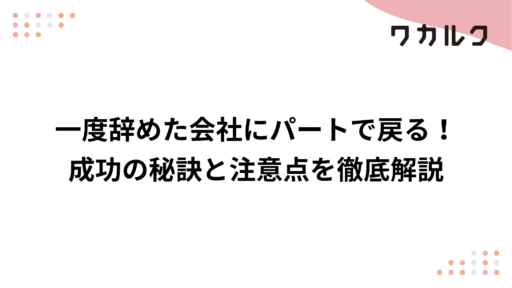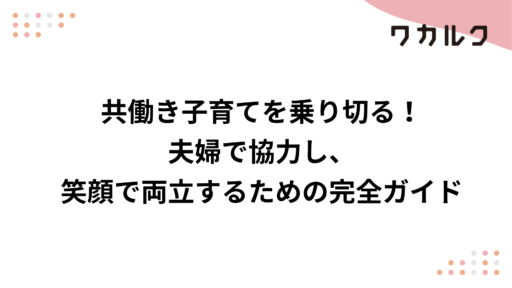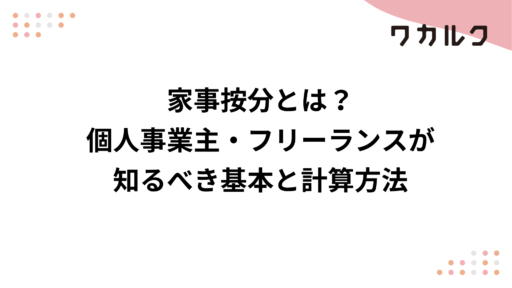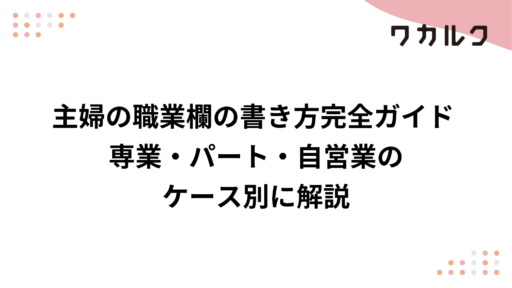
ワンオペ とは?その意味と育児・仕事での実態、乗り越えるための解決策
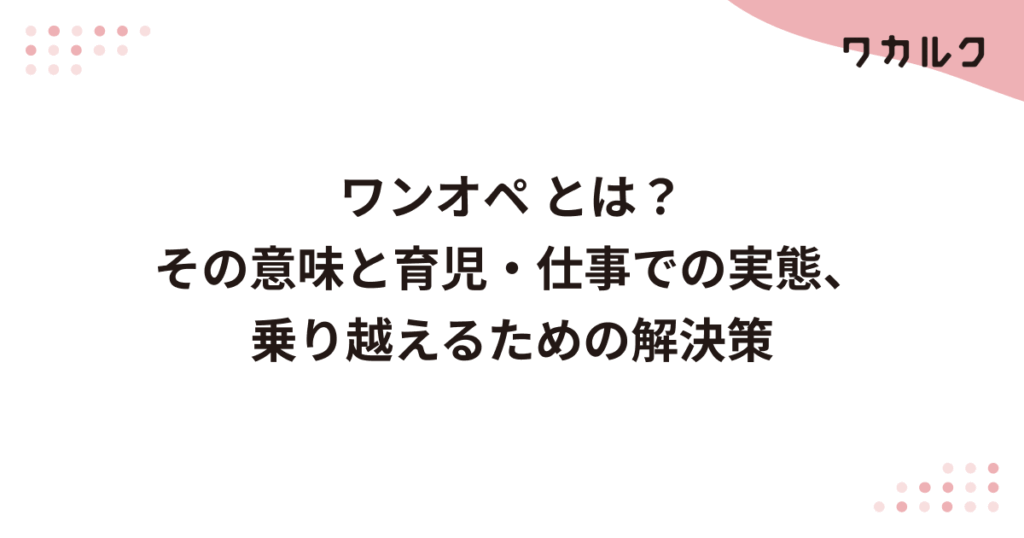
「ワンオペ」という言葉を、ニュースやSNSで目にする機会が増えていませんか?もともとは飲食店の過酷な労働環境を指す言葉でしたが、今や育児や介護、職場など、私たちの生活のあらゆる場面で「一人きりで奮闘せざるを得ない状況」を意味する言葉として使われています。この見えない負担は、当事者の心と体を静かに蝕む深刻な社会問題です。
この記事では、ワンオペがなぜ発生するのかという構造的な原因から、当事者が抱えるリアルな悩み、そしてその過酷な状況を乗り越えるための具体的な解決策までを徹底解説します。読み終える頃には、一人で抱え込まずに周囲と協力し、自分らしい時間を取り戻すための具体的な一歩が見つかるはずです。
目次
1.ワンオペの基本的な意味と使われる場面

1.1.「ワンオペ」の語源と一般的な定義
「ワンオペ」は英語の one-operation を短縮した日本独自の言い回しで、一人で店舗や業務を回す状況を指します。2014年に牛丼チェーン「すき家」の深夜勤務における過酷な労働実態が社会問題となったことを大きなきっかけとして広まり、現在は家事や育児など家庭内の負担が一人に偏る状況にも使われています。便利な略語として定着した一方、当事者が長時間労働や過重負担を強いられやすいネガティブワードとして社会問題化しています。
1.2.特に問題視される「ワンオペ育児」とは
ワンオペ育児とは、主に配偶者の長時間労働や単身赴任などを背景に、家事と育児を事実上一人で担う状態を指します。父親の家事・育児時間は増加傾向にありますが、内閣府が引用した2016年の調査によると、6歳未満の子を持つ父親の家事・育児関連時間は1日平均83分でした。また、同調査では約64%の父親が「調査日に15分以上の育児をしなかった」とされていますが、これは「恒常的に育児をしていない」ことを意味するものではなく、他の調査では「全く育児をしない」と回答した父親は1割強という結果も出ています。(gender.go.jp)
1.3.職場におけるワンオペの事例
飲食店やコンビニでは、人手不足とコスト削減を理由に深夜帯を一人体制で運営するケースが増加しています。2024年11月頃、セブン-イレブンが深夜のワンオペレーションを前提とした防犯策を強化する新システムを導入したと複数のメディアで報じられました。この動きに対し、過重労働を固定化するのではとの懸念も示されています(千葉日報オンライン報道)。(chibanippo.co.jp)
2.なぜワンオペになるのか?その背景と主な原因
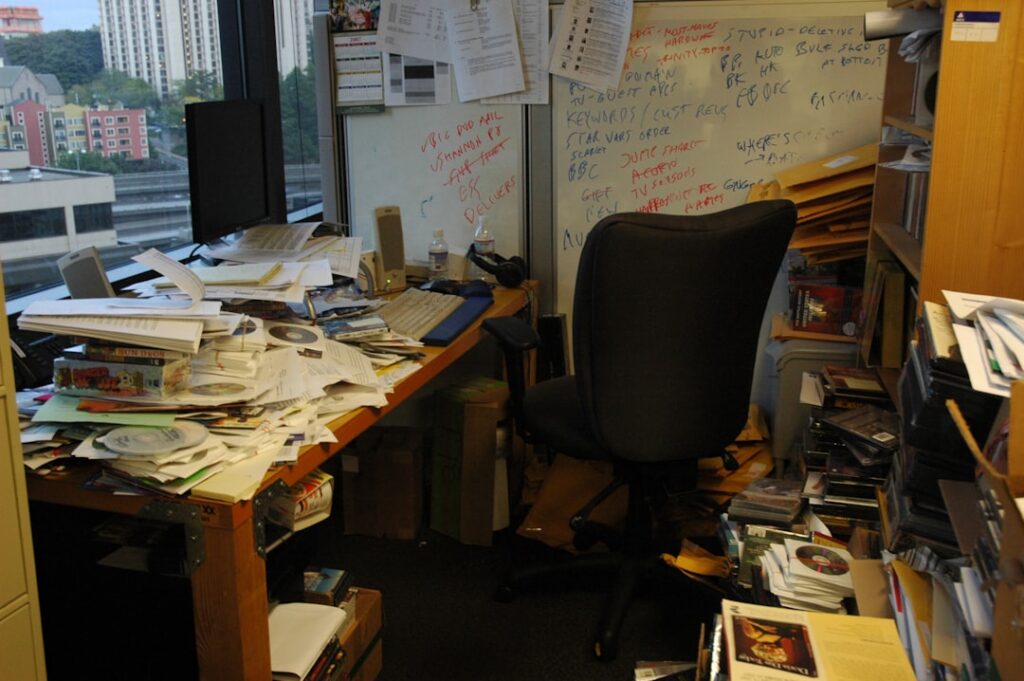
2.1.ワンオペ育児に陥りやすい家庭の状況
総務省の2021年社会生活基本調査によれば、6歳未満の子を持つ夫の家事・育児関連時間は1日あたり平均1時間54分と、妻の7時間28分に比べて極端に短いのが現状です。(soumu.go.jp)
こうした状況は、以下のような要因が重なることで深刻化します。
- 配偶者の長時間労働や深夜勤務
- 単身赴任や転勤による不在
- 祖父母が遠方に住みサポートが得にくい
- 育児への意識差や「家事は妻の仕事」という固定観念
これらの要因が重なると、家事と育児のタスクが特定の一人に集中しやすく、慢性的な負担が常態化します。
2.2.職場環境や社会構造がもたらすワンオペ
人手不足、業務の属人化、そしてコスト削減はワンオペ勤務を生みやすい土壌です。育児・介護休業法が改正され、2025年4月1日から男性育休取得率の公表義務が従業員300人超の企業へ拡大されるなど改善策が進んでいますが、制度利用率向上には職場風土の変革が不可欠と指摘されています(厚生労働省改正ポイント資料)。(mhlw.go.jp)
3.ワンオペの実態と深刻な問題点・リスク
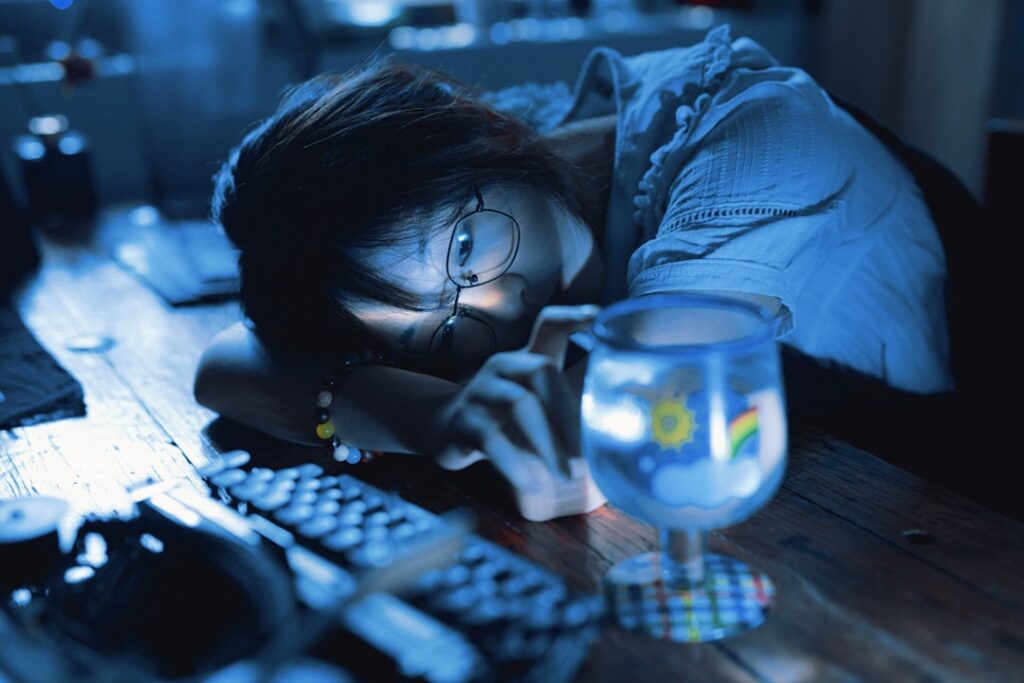
3.1.ワンオペ育児がもたらす具体的な負担と悩み
ワンオペ育児当事者を対象とした複数の調査によると、多くの人が精神的・肉体的な負担を抱えていることが示されています。例えば、ある民間企業の調査(2021年発表)では、0〜1歳児の母親の68%が「自分の時間が少ない」ことにストレスを感じていると回答しました。また、別の調査では7割以上の女性が子育て中に孤立や孤独を感じた経験があると報告されており、ワンオペ育児が慢性的な疲労につながることも指摘されています。
3.2.身体的・精神的な健康への影響
筑波大学などの共同調査によると、出産後1年未満の母親の24%が産後うつの可能性があると判明しました。コロナ禍による孤立や経済不安が長期化し、従来の約10%と比べ倍増しています(NHK報道)。(www3.nhk.or.jp)
3.3.家族関係や子どもの発達への影響
育児における過度な負担は、配偶者間のコミュニケーション不足を招き、夫婦関係の悪化を引き起こす一因となり得ます。ピジョン株式会社が2024年に行った調査では、0〜3歳の子どもを持つ親が感じる育児の苦労として「夜泣きなどによる睡眠不足(46.0%)」や「自分の時間の確保ができない(44.4%)」などが上位に挙げられており、こうした負担が夫婦間のストレスにつながる可能性が示唆されます。(prtimes.jp)
3.4.職場におけるワンオペが引き起こす問題
コンビニエンスストアなどでの深夜ワンオペ勤務は、長時間労働や過重労働につながるだけでなく、防犯・災害時のリスクを高めることが問題視されています。セブン-イレブンにおいても、過去の犯罪被害や従業員の過労問題が、安全策を導入する背景にあると指摘されています。(chibanippo.co.jp)
4.ワンオペを乗り越えるための具体的な解決策と心構え

4.1.パートナーとの協力体制を築くためのコミュニケーション
- タスクを可視化し、家事と育児の一覧を共有
- 週に一度は負担や要望を話し合う機会を設定
- 「ありがとう」を言葉で伝え合い小さな成功体験を積み重ねる
ピジョン調査では、出産前から役割分担を話し合った夫婦の79.1%が「チーム育児」を実践できています。(prtimes.jp)
4.2.外部サービスや公的支援を積極的に活用する
- ベビーシッター
- 家事代行
- 一時保育や病児保育などを担うファミリーサポートセンター
市川市では、経済的負担が少ない1時間500円から柔軟な支援を受けられます。この事業については2024年6月の市川市議会でも議論されています。(city.ichikawa.lg.jp)
4.3.ひとりで抱え込まず、周囲に頼る勇気を持つ
友人・親族・地域コミュニティはもちろん、オンライン育児サロンや自治体の相談窓口も活用しましょう。「助けて」と言えない状況は心身に大きな影響を及ぼし、国立成育医療研究センターの調査では、育児中に誰にも相談できず孤立していると感じる母親は、産後うつのリスクが高まることが示唆されています。(ncchd.go.jp)
完璧主義を手放し、頼る勇気を持つことが、自分と家族を守る第一歩です。
4.4.完璧を目指しすぎない「ほどほど」の心構え
料理は冷凍ストックやミールキットを活用し、掃除はロボット掃除機に任せるなど「手を抜く技術」を取り入れると可処分時間が増え、精神的余裕が生まれます。
4.5.自分の時間を作る工夫とリフレッシュの重要性
早朝や子どもの昼寝時間に10分でも読書する、パートナーと交代で外出するなど「短時間リフレッシュ」はストレス軽減に有効です。
OECDデータによると、日本の男女の無償労働時間には以下のような大きな差があり、意識的な時間創出が不可欠です。
| 対象 | 1日あたりの無償労働時間(平均) |
| 日本の男性 | 41分 |
| 日本の女性 | 224分 |
5.まとめ ワンオペの状況を改善するために

ワンオペは当事者一人の努力で解消できる問題ではありません。個々人が支援を求めやすい雰囲気を作ると同時に、企業・自治体・国が連携し、育児や働き方に関する制度を実効性のある形で運用することが不可欠です。ワンオペを「個人のがんばり」で終わらせず、社会全体で支え合う仕組みづくりが求められています。
また、多様の働き方をしていきたい方におすすめ、リモートワークでキャリアを築くための小さな一歩を安心して踏み出せるようサポートするコミュニティ型スクール、「リモチャン!」。リモチャン!を通じて、ぜひあなたも一歩踏み出しませんか。リモチャン!公式LINEで情報発信中です。